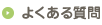事業の概況(令和5年度)
営農指導事業
地域農業は、農業従事者の高齢化や後継者不足が本格化し、農業就農人口が大きく減少していることから、持続可能な農業者の生産基盤確保のため、行政との連携による農地の集約化等に向けた取組みを進めるため、農地利用調整のアドバイスを行いまた、行政と連携した「地域計画」の策定支援により両市合わせて89集落・59%の策定状況となりました。
「みどりの食料システム戦略」においては、秋耕・長期中干しによる温室効果ガスの削減や、水田からの濁水防止・浅水代かきなどの環境負荷軽減技術の普及を行いました。また、肥料高騰による国の緊急支援である「肥料価格高騰対策事業」においては、土壌診断結果に基づく施肥設計や有機質肥料の施用等による化学肥料低減技術の提案を行い、春肥では662名へ38,221千円の申請支援を行いました。
継続的な米穀の需給均衡や価格安定に向け、地域農業再生協議会と一体となり、麦・大豆・非主食用米並びに、多様な担い手による野菜・花卉等の園芸作物との組み合わせにより、米の計画生産と水田のフル活用を推進しました。
県内最大産地として形成されたタマネギ(34ha)・ブロッコリー(27ha)・白ねぎ(6ha)では、耐病性品種の導入と早生・晩生品種の組合せにより収穫期を分散することで、労働力の分散と安定生産が行えました。また、加工業務用野菜では、新たにブロッコリーや白ねぎの出荷を開始し、実需者の加工規模・規格に応じた出荷により信頼ある産地づくりを行いました。
花卉や希少性のある地域特産物のみょうが・山椒をはじめ、多品目野菜については、多様な担い手による生産者の拡充を行い、インショップ向けの品目を充実し「北近江野菜」ブランドの市場認知度が向上しました。
将来の地域農業を担う農業関連の人材支援においては、新規就農者への支援をはじめ、行政が主催する農業塾への支援や、地元農業高校と農業学習を深めるためのコンソーシアムに携わり、課題学習プロジェクトの支援を行いました。
出向く営農経済渉外活動については、担い手経営体への農地集積が加速される中、訪問農家の見直しを行い、TAC112経営体、営農経済渉外員211経営体へ対し、延べ4,635回の継続的な訪問活動と個別事業提案を実施しました。また、統括支店の営農担当を本店へ集約し、営農相談業務の統一化を行いました。
営農情報の発信をスピーディーに行うことが重要であることから、DX化による営農情報の発信と営農相談活動を開始し、営農情報発信ツールとして公式アカウントの開設準備を開始しました。
営農担当者の資質向上においては、営農担当の若手職員を中心に、毎月2回のフォローアップ研修や、関係機関による研修会に積極的に参加するとともに、実践型圃場実習として生産現場に出向き、知識向上と営農担当者としてのレベルアップを図りました。また、個々に実践した営農事業の実績進捗を「営農指導活動実績発表」として共有し営農担当者同士の資質向上を図りました。
利用事業
施設の機能集約については、長浜カントリーをメイン施設として位置付け、籾摺調製作業や小麦精選作業を集約することで、稼働時間や管理費の削減を図りましたが、電気料金の高騰や施設の老朽化に伴う修繕費の増加などにより、施設運営は大変厳しい状況となりました。
長浜北部荷受センターにおいては、施設の老朽化により持続可能な施設運営を行うことが困難なことから、令和5年産米をもって稼働を中止することを決定し、利用者への周知を行いました。
さらに、大麦・大豆の乾燥・調製の基幹施設である神照カントリーをサブ施設として位置付け、老朽化した施設の更新・改修による機能強化について協議を行いました。
また、施設の保守点検整備にあたっては、専門技術職員による継続的な修繕コストの削減を図るとともに、JA間連携によるプラントメンテナンス受託業務を行いました。
米のカントリー利用については、担い手経営体のニーズに対応した施設の有効活用や、飼料用米の取組み拡大を行いましたが、作柄の影響により荷受重量は前年対比84.9%で2,794トンの実績となりました。
麦類のカントリー利用については、小麦では収穫前後の天候不順の影響を受け赤かび病や発芽粒が多発し、荷受重量は前年対比86.0%で1,560トンの実績となりました。
大豆のカントリー利用については、干ばつや播種遅れの影響を受け、荷受重量は前年対比78.0%で255トンの実績となりました。
育苗については、水稲苗では施設の有効活用を図るため、JA間連携による取扱数量において2ヶ年の覚書を締結し、最低供給数量50,000箱の計画的かつ安定的な供給体制を構築することができましたが、離農による利用者の減少により前年対比98.1%で181,114箱の実績となりました。
また、園芸苗では、生産振興と連動し新たに白ねぎの供給を開始しましたが、令和6年産タマネギの作付け減少により、前年対比71.6%で3,678千本の実績となりました。
販売事業
主食用米の集荷では、生産者との事前契約の更なる徹底を図るとともに、実需者との結びつきにより、収穫前契約や複数年契約等の事前契約率を96.2%と高め、確実な結びつきを行いましたが、作況が98のやや不良となったことから、集荷実績は前年対比92.1%で、地場集荷81,647袋、カントリー集荷40,182袋、合計121,829袋となりました。
水田活用米穀の集荷では、作柄変動による作況調整が実施され、加工用米10,522袋、輸出用米3,069袋、米粉用米1,705袋の合計15,296袋となり、飼料用米は643トンの実績となりました。
麦類においては、農林61号495トン、びわほなみ279トン、ファイバースノウ572トンとなり、麦類全体では前年対比84.5%の1,346トンとなりました。また、大豆は前年対比65.9%で10,122袋となりました。
園芸品目の販売品取扱高は、白ねぎと加工業務用タマネギ・キャベツの取扱い増加により、買取販売1億円・受託販売63百万円となり前年対比116.4%で1億63百万円の実績となりました。
全体の販売品取扱高は、前年対比104.3%で11億77百万円の実績となりました。
購買事業
生産資材

世界情勢の影響により肥料原材料価格が高騰しましたが、産出国からの輸出制限の緩和から一定の価格緩和となりましたが、高騰前の価格まで回復せず依然として高止まり傾向となっております。こうした中で、肥料の統一銘柄については、早期仕入によるスケールメリットを生かした価格設定と、大口利用特別価格を設定し生産資材の安定供給を行いました。取扱高は前年対比94.0%、6億29百万円となりました。
また、JAグループが進めるDX化の推進と一体となり、AI-OCRによる予約申込書のデジタル化に取組みました。
生活物資

生活資材については、組合員のくらしの支援に向け、灯油の定期配送や「くらしの宅配便」については、広報紙等を通じて普及拡大を行いました。
新たに、近隣JAとの健康器具等の合同展示会を開催いたしましたが、前年度のLPガスの事業譲渡により取扱高は前年対比53.9%、2億19百万円となりました。
信用事業
JAを取り巻く金融環境は、長引く金融緩和政策の見直しや為替相場の変動などにより、物価の上昇や金利の上昇など組合員・利用者の生活に影響が出始めています。
こうした中、総合渉外担当者を中心に、ライフプランやニーズに合わせた金融商品・サービスの提供を軸に、各種ローンの伸長、年金獲得を主とした取引メイン化に取組みました。結果、年金口座については573件の獲得となりました。しかしながら、貯金残高においては、地方公共団体の貯金が大きく減少したことや個人貯金の減少により前年対比98.2%、1,432億5百万円となりました。
貸出金においては、農業法人・担い手農家の農業経営の安定・成長に向けた農業融資の提案に取組み、年間20件92百万円の獲得となりました。
一方、住宅ローンについては、専任担当者の営業推進の強化等により、年間30件11億6百万円、マイカーローンについては、次世代への普及推進に取組み、年間151件3億84百万円の獲得となりました。結果、貸出金全体で191億66百万円の実績となりました。
有価証券の運用については、優良格付け債券を前提として、ポートフォリオの構築、リスクの軽減、安定した利息の確保ができるよう取組みました。結果、有価証券残高は前年対比106.3%、182億89百万円の実績となりました。
共済事業
少子高齢化に伴う人口減少が続く厳しい状況の中、契約者との関係性強化・再構築に向け、3Q活動(寄り添う活動)をLA・スマイルサポーターを中心として6,828人に実施し、組合員・利用者に「ひと・いえ・くるま・農業」のバランスの取れた総合保障を提供しました。共済普及実績においては、共済事業向けの総合的な監督指針の改正により推進体制の見直しを行い、共済推進の目標設定を自主目標に切り替えた結果、長期共済保有高で2,638億7百万円(前年対比95.2%)、短期共済新契約掛金で5億77百万円(前年対比94.9%)となりました。
また、利用者の利便性向上とLA等の事務負担軽減を目的に、普及情報システム(コロンブス)を活用した活動管理、Lable't s(タブレット端末機)を活用した契約手続き及びキャッシュレス・ペーパーレス手続き、Webマイページ・JA共済アプリなど各種施策の取組み促進に向けてデジタル技術等を活用しました。短期共済の主力商品である自動車共済では、事故処理の迅速化・適正化に努めるとともに、契約者満足度向上に取組みました。
契約者への共済金支払状況は、長期共済(生命)1,163件支払額6億5百万円、(建更)219件支払額87百万円、短期共済(自動車共済等)1,028件3億32百万円で、合計2,410件10億24百万円の支払いとなりました。
生活指導事業

組合員や地域住民のみなさまが安心して暮らせる地域づくりと心豊かな暮らしの実現に向けて農業者・組合員組織や関係団体と連携しながら取組みました。
女性部のグループ活動ではヨガ教室等の6講座に92名の参加があり、うち5名が女性部に新しく加入され、女性組織の活動を通じて交流の輪が広がりました。
女性部の地域貢献活動では、エコキャップの回収運動、能登半島地震支援募金やユニセフ募金を行いました。コロナ禍を乗り越え、助け合い組織にじの会「ふれあいサロン」を再開し、13集落から申込を受け223名の参加がありました。
JAくらしの活動では料理・寄せ植え講習会・味噌作り教室等の7講座に215名の参加があり、楽しい仲間づくりができました。
健康増進(健康診断・健康指導)活動では138名の受診と結果指導に88名の参加がありました。
食農教育活動では、3校の小学生を対象にした白ネギの収穫体験や親子を対象にした農業体験に7組の家族の参加がありました。
また、JAグループの食農教育をすすめる子ども雑誌「月刊誌ちゃぐりん」を管内の小学校と公設児童クラブ、山東図書館、近江図書館、長浜図書館へ寄贈し、いのち・自然・食物・農業の大切さを伝える取組みを行いました。
さらに、広報活動では広報誌「ふれあい」を毎月12,000部発行し、ホームページやインスタグラムを通じてJA事業や身近な情報、SDGsの取組状況等の情報発信に取組みました。
介護福祉事業

組合員や地域住民のみなさまが住み慣れた地域で、安心して生活が続けられるように身体の介護や生活援助のサービスを行いました。
訪問介護事業では、身体介護33百時間、身体生活介護12百時間、生活援助16百時間、介護予防6百時間の総合計67百時間の介護サービスを提供しました。